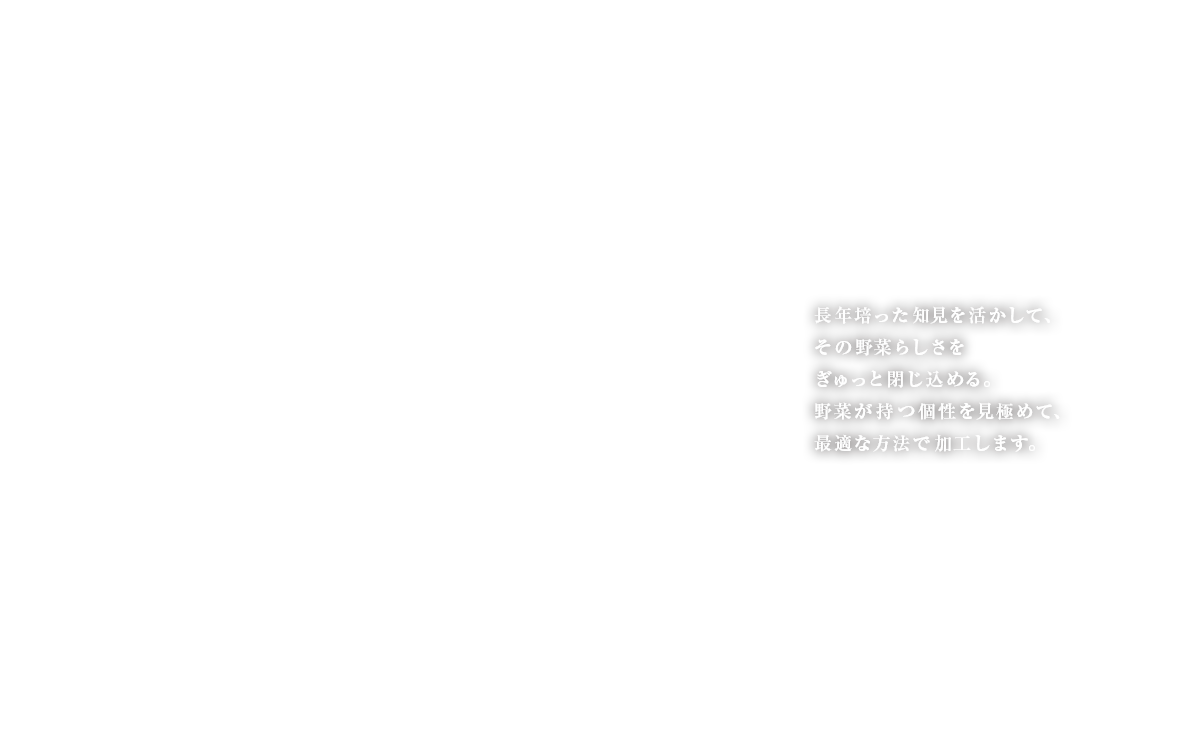

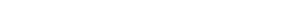

ぎらぎらと強い日差しが照りつける8月。栃木県の那須工場には、おいしさも栄養もピークに達した真っ赤なトマトが全国から続々と入荷します。トマトをしぼるのは盛夏の2ヶ月間だけ。その間、工場は24時間体制で稼働し、旬のトマトのおいしさを逃さずジュースにしていきます。
トマトジュース、トマトピューレ、トマトケチャップなど、カゴメにはさまざまなトマト加工品があります。それぞれの商品に合ったトマトのおいしさを引き出す――。100年以上の歴史の中で、カゴメはその技術を磨き、知見を蓄えてきました。
「真っ赤に熟れたトマトを畑でガブッとかじった時のみずみずしさ、そして、口の中に広がる深い甘み。そんなトマトのおいしさを目指しました」と、那須工場の松本健一は話します。

▲全国から入荷したトマトのこの壮大な風景が見られるのもこの時期だけ。


▲届いたトマトは綺麗に洗浄され、人の目と手によって選別が行われています。

 「おいしさのためには、熱履歴を減らし、出来るだけスピーディに加工することが重要」と語る那須工場の松本。
「おいしさのためには、熱履歴を減らし、出来るだけスピーディに加工することが重要」と語る那須工場の松本。
そこで採用されたのが、しぼり方が違う2種類のトマト果汁をブレンドすることでした。ひとつは、ゆるやかにしぼって爽やかな風味を抽出したトマト果汁。これをカゴメが特許を持つRO技術で濃縮しています。RO濃縮技術とは、かかる熱を最小限に抑えて、トマト特有の爽やかさや鮮やかな赤色をしっかり残すことができる濃縮方法です。もうひとつは、強めにしぼって深みのある味わいを抽出したトマト果汁。これは、低圧で水分を飛ばし、安定した品質を保つ方法で濃縮されています。
このような2種類のトマト果汁を絶妙の割合でブレンド。それは1回きりの搾汁では、絶対に出せないおいしさ。まさに、畑で採れたトマトのようにさらっとしていて、しかも深みがある、そんな味わいを「つぶより野菜」でぜひ感じていただきたいと松本は話します。

 熱を加えないRO技術で濃縮されたトマト汁は色が鮮やかで、香りも豊かです。
熱を加えないRO技術で濃縮されたトマト汁は色が鮮やかで、香りも豊かです。


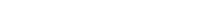

にんじんは糖度が高いのにもかかわらず、特有の香りによって、苦手と感じる方が多い野菜です。「カロテン等の栄養豊富なにんじんをもっとたくさんの方に、おいしく飲んでいただきたい」。そんな考えから生まれたのが、カゴメの「フレッシュスクイーズ」製法です。フレッシュスクイーズ製法とは、熱をかけずに「やさしくゆっくりつぶしながら」しぼっていく技術。これにより雑味が少なく、体にすっとしみ込んでいくようなおいしさが実現しました。もちろん「つぶより野菜」にもこの製法を採用。まろやかなにんじんの味わいが、全体をやさしく包み込むようにまとめています。


 機械を稼働させながらも、品質のチェックは常に行います。
機械を稼働させながらも、品質のチェックは常に行います。
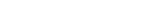
長野県にある富士見工場では、レタス、セロリ、ほうれん草、プチヴェールなどの「葉野菜」が搾られています。
「葉野菜は、トマトやにんじんなどに比べて、鮮度や香りが失われやすい野菜。収穫したら、いち早く加工することが必要なんです」と富士見工場の高田貴志が話します。「富士見工場は葉野菜の主要産地からアクセスしやすい位置にあるので、葉野菜を新鮮なうちに加工することができるんです」。――よい原料を、よい状態のまますばやくジュースにする。「畑は第一の工場」。その考え方は、昔から変わらず守られ続けてきたカゴメの伝統とも言えるのです。
「葉野菜加工の鍵を握るのがブランチングという工程です」と高田は言います。ブランチングとは、おいしさを引き出すために、野菜に最低限の熱を通すことです。深い甘みや、全体の味を引き締める苦み。こうした、葉野菜特有のおいしさは、ブランチングのさじ加減で決まってきます。


▲富士見工場は、南アルプス山系を望む、自然豊かな地にあります。


▲洗浄されたレタスは人の手によって選別され、熱湯の中をくぐります。

 「必要以上の熱は逆効果。野菜の個性を見極め、ぴったりの時間を決めています。」と語る富士見工場の高田。
「必要以上の熱は逆効果。野菜の個性を見極め、ぴったりの時間を決めています。」と語る富士見工場の高田。
しぼられた野菜汁は、非常に細かい網目から漉し出されサラサラのジュースになっていきます。この網目のサイズは、なめらかな豆腐づくりに採用されている網目と同じ大きさ。デリケートな野菜を、細心の注意を払ってしぼります。
「葉野菜はどちらかというと引き立て役かも知れません。でもこの野菜がないと味が引き締まらない、この野菜があるからこそ味に深みが生まれる。『つぶより野菜』に入っているのはそんな国産野菜ばかりです。どの野菜が欠けてもこのおいしさは成立しなかった。だからこそ私たちは、その個性をしっかりしぼる、しっかり引き出す――。そんな想いで野菜と向き合っています」。高田はそう話します。



▲粉砕を終えたレタスは搾汁の過程へと進み、非常に細かい網目から漉し出されサラサラのジュースになっていきます。

生でシャキシャキとした食感が特徴のレタス。葉が薄く熱の通りが早いため、ブランチングの時間は最小限にとどめ、レタス特有のかすかな苦みが残るジュースに仕上げます。

旬の冬には糖度が一番高くなるプチヴェール。葉や茎が固いので、搾汁の圧力を高めにしてしぼっていきます。

独特の香りを持つセロリ。ほかの野菜に比べると、おいしさを妨げる硝酸態窒素が多く含まれています。これを加工の段階で最小限に抑えます。

晩冬にはほうれん草が旬を迎えます。ほうれん草のえぐみの原因となるシュウ酸を取り除き、甘さを引き出します。レタス同様、葉が薄く繊細なので、最小限の力で加工します。
上記に代表されるようなひとつひとつの野菜の個性に合わせて選んだ最適な搾汁・濃縮方法。「つぶより野菜」には、6種類の野菜の、いちばんよい状態のおいしさが詰まっています。